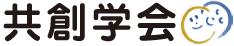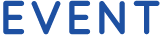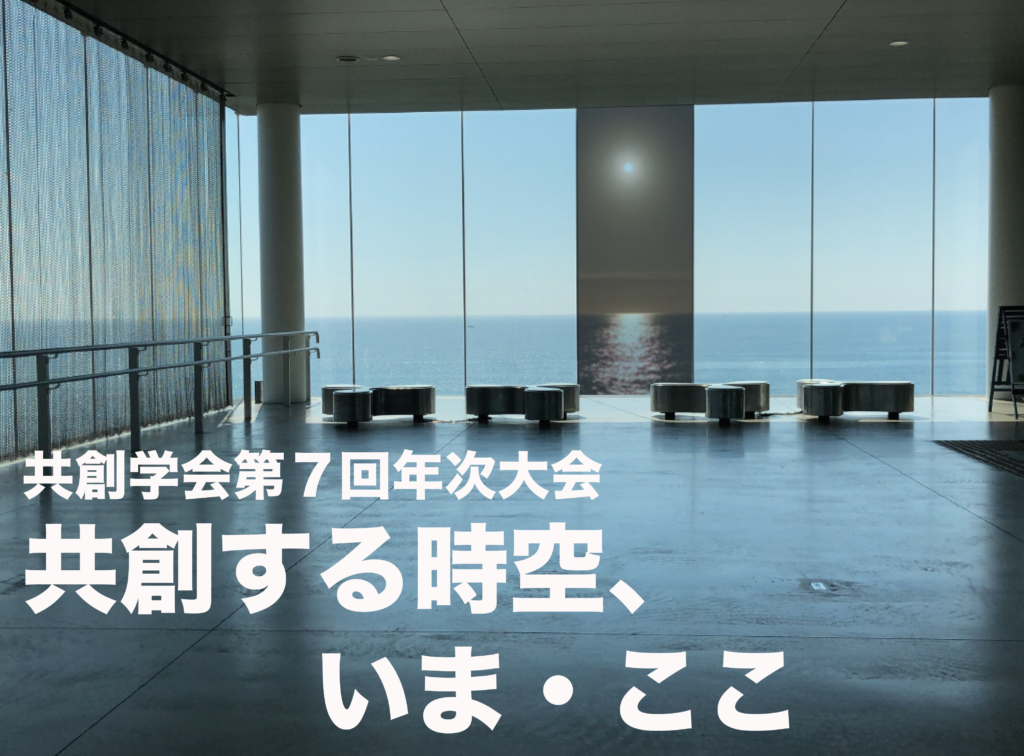
共創学会第7回年次大会「共創する時空、いま・ここ」
日時:2023年12月8日(金),9日(土),10日(日)
場所:日立シビックセンター(茨城県日立市幸町1-21-1)
主催:共創学会
招待講演 プログラム OS/WS企画 予稿原稿 参加登録 アクセス お問い合わせ
大会テーマ:「共創する時空、いま・ここ」
スマートフォンが生まれて、その後コロナ渦で一気に進んだネットワークの世界。個別化された物事が、利益・能力・意義・理由、そして「いいね」やフォロワーの数などの合理性に基づいて接続され最適化される世界で、私たちは本当に幸せにつながる共創ができてきたのでしょうか。本年次大会では,過去(記録)や未来(予測)をデータ化して、合理性によって時間や空間を貼り合わせて伸張してきたテクノロジーや社会構造を見つめ直し、また、その中で、「いま・ここ」で実践することの意義を再認識できればと考えています。
茨城県日立市は、日立製作所や日立鉱山に代表される工業の町ですが、様々な年代の地層が複雑に折り重なり、海と山、森と川が間近に迫るダイナミックな自然が味わえる、落ち着いた、気持ちの良い土地です。きっと皆様に良い体験と、交流の機会を提供できるかと思います。
実行委員長 笹井一人
大会プログラム 詳細PDF
| 第1日目:2023年12月8日(金) | ||
| 16:00-18:00 |
一般公開セッション OS/WS企画(多用途ホール・102室(期間中)) 「アートの転回:『わたし』における世界の感じ方」 代表者:郡司ぺギオ幸夫(早稲田大学) |
|
| 第2日目:2023年12月9日(土) | ||
| 10:00-12:00 |
一般公開セッション |
一般公開セッション OS/WS企画(702-704室) 「版画と建築」 代表者:植原雄一(株式会社植原雄一建築設計事務所) 田中彰 |
| 12:00-12:50 | 受付(多用途ホール前ホワイエ)当日登録・クローク(701室) | |
| 12:50-13:00 | 開会の挨拶(多用途ホール) | |
| 13:00-13:50 |
招待講演1(多用途ホール) |
|
| 13:50-14:40 |
招待講演2(多用途ホール) 「シオマネキにおけるProto metacognitionの可能性:空間認知と社会行動の共進化の果て」 村上 久(京都工芸繊維大学) |
|
| 14:40-15:00 | 休憩 | |
| 15:00-16:00 | インタラクティブ発表A(多用途ホール) | |
| 16:00-17:00 | インタラクティブ発表B(多用途ホール) | |
| 17:00-18:00 | 休憩 | |
| 18:00-20:00 | 懇親会(多用途ホール) | |
| 第3日目:2023年12月10日(日) | ||
| 9:00-10:30 | 口頭発表1(502室) | 口頭発表2(702-704室) |
| 10:50-12:20 | 口頭発表3(502室) | 口頭発表4(702-704室) |
| 12:20-13:10 | 昼食 | |
| 13:10-14:40 | 口頭発表5(502室) | 口頭発表6(702-704室) |
| 14:50-15:00 | 閉会の挨拶・振り返り | |
| 15:00-17:00 |
一般公開セッション |
一般公開セッション OS/WS企画(702-704室) 「ミニ・ヒューマンライブラリー:マジョリティが纏う特権について考えてみよう!」 代表者:福村真紀子(茨城大学) |
心の中で感じている自分の身体(=心の中の身体)は、自分の身体に対する意識的体験であり、その意識的体験は目に見えない。そのため、心の中の身体は古くは哲学的な問題として扱われてきた。しかし、1998年に心の中の身体を操作する実験心理学的手法が開発され、現在は心の中の身体の認知メカニズムを調べることができるようになった。本講演では、従来の心の中の身体の操作手法にバーチャルリアリティ技術を融合させることで明らかになってきた、心の中の身体の形成過程と脳内表現、そして、心の中の身体と運動能力の関係について紹介する。
松宮 一道(東北大学)

2000年 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 博士課程修了。博士(工学)。同年、カナダ・ヨーク大学 視覚研究所 博士研究員。2002年 東京工業大学 像情報工学研究施設 研究機関研究員。2004年 ATR人間情報科学研究所 専任研究員。2005年 東北大学 電気通信研究所 助手。2007年新職階制移行により同助教。2014年同准教授。2016年JSTさきがけ研究者兼任。2018年 東北大学 大学院情報科学研究科 教授、現在に至る。2017年に第13回日本学術振興会賞、2023年に令和5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門)を受賞。専門は心理物理学。
シオマネキにおけるProto metacognitionの可能性:空間認知と社会行動の共進化の果て
自己意識や反省的意識はヒトを特徴づけるとされてきたが、現代では霊長類をはじめいくつかの分類群もこれらを持ちうると考えられている。「人間のような」高次の認知の有無をテストする課題に特定の動物はパスできると考えられている。しかし「人間のような」認知の有無を問うのではなく、その進化的起源を辿るには動物の身体を含む生態学的コンテクストを踏まえた実験が必要ではないか。本研究ではシオマネキというカニを対象とし、社会行動と空間認知の関係を検証する実験から、そのヒントを探る。結果としてこのカニは、巣穴位置に関する2種類の記憶(運動に直結する記憶とそれを評価するシステム)を持つことが示唆された。ここから空間認知と社会行動の共進化の果てに原初的なメタ認知が出現してきた可能性を議論する。
村上 久(京都工芸繊維大学)

2015年神戸大学大学院理学研究科博士課程後期課程終了、博士(理学)。早稲田大学基幹理工学部博士研究員、神奈川大学工学部特別助教、東京大学先端科学研究センター特任助教を経て、2021年より京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系助教。ミナミコメツキガニ、オキナワハクセンシオマネキ、アユ、ヒト(歩行者など)を対象としながら、群れ行動、探索行動、ナビゲーションに関する計算機モデル構築と実験を行なっている。
12/08(金) 16:00-18:00
「アートの転回:「わたし」における世界の感じ方」
代表者:郡司ぺギオ幸夫(早稲田大学)
12/09(土) 10:00-12:00
「版画と建築」
代表者:植原雄一(株式会社植原雄一建築設計事務所) 田中彰
「共創を拓く~文化施設は共創の場となるか」
代表者:横山歩(公益財団法人神奈川芸術文化財団)
12/10(日) 15:00-17:00
「池袋カフェlampの共創」
代表者:浦上大輔(日本大学)
「ミニ・ヒューマンライブラリー:マジョリティが纏う特権について考えてみよう!」
代表者:福村真紀子(茨城大学)
■口頭発表
形式
・口頭発表は大勢の参加者を対象にスライド等を用いて発表する形式です。
・パラレルセッション(2会場、6セッション)とし、各セッションが特定領域に偏らぬよう配慮しています。
会場
・日立シビックセンターの502室または702-704室です。
・ご自身の発表詳細についてはプログラムにてご確認ください。
時間
・発表15分、質疑応答10分です。
・各セッションでは、質疑応答を含む発表全体の進行は座長が取り仕切ります。
・発表終了3分前(12分)に一鈴、15分に二鈴で合図します。
運営が準備するもの
・スクリーン、プロジェクター、マイク、プロジェクター用の接続コード(変換プラグはなし)。
発表者にご準備いただくもの
・PC:スライドの投影については、基本的にご自身のPCを持ち込んで実施してください。(PCを持ち込めない特別な事由のある方は必ず事前に申し出てください。相談に応じます。)
・スライドで発表を行う方は、HDMI端子あるいはVGA出力端子(D-Sub15ピン)のあるPCでしたら事務局の準備する接続コードで接続できます。それ以外の端子のPCをお使いの場合は、変換プラグを各自でご用意ください。なお、Macを使われる方は、Mac用のVGA出力端子/HDMI端子への変換プラグを各自でご準備お願いいたします。
メディアチェックと出席確認
・各セッションの30分前からメディアチェックを受け付けます。発表者は、セッション開始の10分前までに、必ずPCの接続確認等のメディアチェックを行ってください。また、座長による出席確認を済ませてください。
その他
・研究の性質や、やむを得ない事情から、オリジナルな発表方法を希望する方はお申し出ください。個別に検討し、可能な限り対応したいと思います。
■インタラクティブ発表
形式
・研究のポスターをパネルに設置し、発表者と参加者がそれをみながら対面で交流する発表形式です。
会場
・日立シビックセンターの多用途ホールです。
・ご自身の発表詳細についてはプログラムにてご確認ください。
時間
・1セッション60分で、2セッション行います。
運営が準備するもの
・パネル、画鋲、椅子
発表者にご準備いただくもの
・印刷された発表用のポスター
パネルについて
・1発表につき、パネルを1枚準備いたします。パネルのサイズは横1200㎝×縦1800㎝です。ポスターは最大A0の大きさで準備してください。
・ポスターの貼り付けは、事務局で準備する画鋲を使用してください。
・インタラクティブ発表の最初のセッション開始の10分前までに、発表番号が示されたパネルにポスターを貼ってください。12/8の大会開始後から貼り付け可能です。
・インタラクティブ発表の2番目のセッション終了後に各自でポスターをはがしてください。懇親会にご参加される方は、懇親会からお帰りになる際でも構いません。
発表準備
・発表者は、ご自身の発表セッション開始10分前にご自身の場所で待機し、事務局からの出席確認をお待ちください(インタラクティブ発表に座長はおりません)。
その他
・パネルが複数枚必要といった特別な事由のある方はご相談ください。
・研究の性質や、やむを得ない事情から、オリジナルな発表方法を希望する方はお申し出ください。個別に検討し、可能な限り対応したいと思います。
重要日程
| (1) | OS/WS申込み締め切り: | 2023年7月28日(金) |
| (2) | 発表申込締め切り: | 2023年 |
| (3) | 予稿原稿の締め切り: | 2023年 |
| (4) | 事前参加申込み締め切り: | 2023年11月26日(日) |
| (5) | 予稿集の公開: | 2023年12月6日(水) |
| (6) | 第7回年次大会: | 2023年12月8日(金)~ 12月10日(日) |
発表申込について
第7回年次大会では、「①口頭発表」および「②インタラクティブ発表」「③口頭発表・インタラクティブ発表のどちらでもよい」の3種類から選択していただけます。「③口頭発表・インタラクティブ発表のどちらでもよい」を選択された場合、発表申し込み状況により、実行委員会で口頭発表、インタラクティブ発表を決定させていただきます。
発表者(連名発表者)のうち少なくとも1名が本学会の会員であることが条件です。
締め切りは2023年9月15日(金)です。※延長しました。
発表受諾の通知は9月中を予定しています。
それぞれ発表枠には限りがあるため、ご希望に添えない可能性があります。その際はプログラム委員会で検討後に、対応を連絡させていただきます。ただし、なるべくご希望に添えるように努力いたしますので、ぜひ積極的なご応募をお願いいたします。
発表ご希望の方は、(1)~(6)の登録内容をあらかじめご準備いただき、以下の「発表申し込みフォーム」から提出してください。
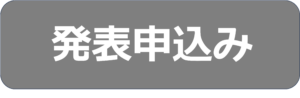 発表申込みは締め切りました。
発表申込みは締め切りました。
申込フォーム記入項目
(1)発表タイトル
(2)著者氏名・所属・メールアドレス・会員番号
(3)発表要旨(800字以下):口頭発表を希望される場合、研究内容と大会テーマ「共創する時空、いま・ここ」の関係が示されることを期待します。テーマに関して詳しくはこちらをご覧ください。
(4)キーワード:以下の〈例〉を参考にキーワードを最大5つご記述ください(〈例〉に無い場合には自由記述可)。「対象」「分野」「方法」の各カテゴリーから1つ以上を記述するのが望ましいですが、難しい場合はそれにとらわれる必要はありません。
〈例〉
対象:表現、コミュニケーション、ファシリテーション、コミュニティ、デザイン、計測、調査、分析、製作、マイノリティ/マジョリティなど
分野:社会、生活、科学、技術、アート、言語、心理、ケア、法、行政、教育、スポーツ、医療など
方法:量的研究、質的研究、理論研究、臨床研究、実践研究、開発研究など
(5)発表形式:①口頭発表、②インタラクティブ発表、③口頭発表・インタラクティブ発表のどちらでもよい、から選択してください
(6)大会事務局への連絡事項:研究の性質(例:言語的な論理のみでは表現しづらい)、やむを得ない事情から、オリジナルな発表のやりかたを希望する方は、お申し出ください。個別に検討し、可能な限り対応したいと思います。。
- 口頭発表
大勢の参加者を対象にスライド等を用いて発表する形式です。発表15分、質疑応答10分を予定しています。発表数により、複数の部屋で同時並行して進行する(パラレルセッション)可能性があります。
- インタラクティブ発表
発表者と参加者が交流する(ポスターの掲示などを用いた)発表形式です。On-goingな内容(未完の研究や、検討段階のアイデアなど)での発表も歓迎します。特に指定がなければ、原則ポスター発表となります。ポスター以外の特別な発表形式も可能な範囲で対応させていただきますので、申込時に希望内容をお書きください。
発表受諾の後、発表に関する予稿の提出をお願いしております。
(1)締め切り:2023年11月17日(金)(延長しました) 以下の予稿提出フォームより提出ください。

予稿の提出は締め切りました。
(2)発表番号について:予稿原稿提出時に必要な情報のひとつとして「発表番号」があります。「発表の受諾」のお知らせの際にお知らせします。
(3)テンプレート:予稿執筆にあたっては、学会のテンプレート(ダウンロードはこちら)を利用し、その執筆要領に従ってください。
(4)概要:原稿の概要には、発表申し込み時にお書き頂いた800文字以内の要旨をそのまま利用するのではなく、原稿テンプレートに沿って300字以下に短縮したものを改めてお書き頂きますようお願い致します。当日に配布するパンフレット(概要集)に掲載されます。
(5)予稿集:予稿集はPDF形式で2023年12月上旬に公開予定です。
テンプレートは以下よりダウンロード可能です。
オーガナイズドセッション企画について(申込みは終了しました。)
共創学会第7回年次大会では「オーガナイズドセッション/ワークショップ(OS/WS)」の提案を募集します。オーガナイズドセッションとは「オーガナイザーがテーマを定め、そのテーマに関連する発表や議論をもくろむセッション」です。
「OS/WS」ですから、通常のWS形式でも構いません。学会の期間中に時間と場所が提供され、自由に利用できるとお考えください。作品の展示なども歓迎します。オーガナイザーが負担する開催費、参加者が負担する参加費とも無料です。つまりOS/WSのみのご参加であれば費用は一切かかりません。
セッションやWSに参加したことはあるけど、運営したことはなかったという方は多いかもしれません。共創学会らしい柔軟なご提案を心よりお待ちしております。
プログラム委員長 澤宏司

申込みは終了しました。
参加をされる方は,以下の参加登録フォームから大会および懇親会への参加登録をお願いします。
事前参加登録の締め切りは2023年11月26日(日)です。それ以降は、「以降の参加登録」となります。
会場受付での参加登録はございませんので、大会前に参加登録を済ませてお越しください。
また、口頭発表・インタラクティブ発表をされる方は、必ず事前参加登録と大会参加費の支払いを完了をしてください。事前参加登録、大会参加費の支払いをされない場合、発表が取り消される場合があります。
大会参加費:
| 区分 | 事前参加登録 | 以降の参加登録 |
| 正会員 | 5,000円 | 6,000円 |
| 準会員 | 3,000円 | 4,000円 |
| 非会員(正会員相当) | 7,000円 | 8,000円 |
| 非会員(準会員相当) | 4,000円 | 5,000円 |
※「準会員相当」とは、「学生など、年会費の減免を希望する方」を指します。
※ 領収書は、原則当日の受付にてお渡しします。
※ 正会員、準会員の参加費は非課税,非会員の参加費は税込みとなります.
懇親会:
懇親会は、9日(土)プログラム終了後にそのままインタラクティブ会場にて実施します。ホテルクオリティの本格的なケータリングとなります。インタラクティブ発表のセッションで収まりきらない議論もしていただけますので、ぜひご参加ください。
| 区分 | 参加費 |
| 懇親会 | 3,000円 |
※ 懇親会の参加申し込みは、極力、事前登録と合わせて申し込みをお願い致します。会場の混雑具合によっては、当日のお申し込みはお断りさせて頂く場合があります。
※ 懇親会費の領収書は、参加費とは別に発行いたします。
※ 懇親会費は税込みになります。
申込みは終了しました。
大会参加費・懇親会費の支払いについて
支払い方法について:
大会参加費および懇親会の支払いは、原則クレジットカードでの支払いをお願いしております。参加登録をお申し込みの方は、以下の支払いページに進み、大会参加費、懇親会費をお支払いください。「事前参加登録」での大会参加費の支払い期限は2023年11月26日(日)となりますのでご注意下さい。それ以降は「以降の参加登録」の大会参加費になります.
特別な事情により銀行振り込みをご希望される場合は、共創学会事務局(sfcc2023_info@nihon-kyousou.jp)まで早めにメールでお問い合わせください。
支払いは終了しました。
キャンセルポリシー:
事前登録締め切り前のキャンセルに対する返金は承りますが、それ以降の返金には応じかねますので、ご留意いただければと存じます。参加申込みのキャンセルをご希望の場合は、年次大会事務局までご連絡ください。
実行委員会
実行委員長:笹井一人(茨城大学)
副実行委員長:谷伊織(神戸大学)
プログラム委員長:澤宏司(同志社大学)
プログラム委員:笹井一人,谷伊織,澤宏司,西洋子(東洋英和女学院大学),三輪洋靖(産業技術総合研究所),郡司幸夫(早稲田大学),三輪敬之(早稲田大学),中村恭子(大阪大学),金尾雄二(障害者総合支援法指定事業所「からしだね」)
出版担当:三輪洋靖
広報担当:谷伊織,西洋子,笹井一人
財務担当:三輪洋靖
大会事務局担当:笹井一人
アドバイザー:三輪敬之,郡司幸夫,金尾雄二,中村恭子
共創学会事務局までお問い合わせください