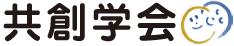会長
西 洋子 Hiroko Nishi
東洋英和女学院大学 教授
<専門分野>身体表現論、舞踊学、応用コミュニケーション科学
<プロフィール>お茶の水女子大学大学院修士課程、神戸大学大学院博士後期課程修了(学術博士)。子どもの身体表現や精神科入院病棟での実践を行う。 1998年から地域社会でインクルーシブダンスを展開。お茶の水女子大学助手、学習院大学講師を経て2004年から現職。NPO法人みんなのダンスフィールド理事長、 国立民族学博物館客員教授(2008-2012)、早稲田大学理工学術院客員教授(2008-)。舞踊学会研究奨励賞(2003)、ISAPA最優秀ビデオ発表賞(2003・2007)受賞。
<メッセージ>多様な人々が、それぞれの身体で、共に表現を創る現場にいます。驚きや困惑、感動があります。今はまだ、切れ端しかつかまらず、泡のようなものしか伝えることができません。 身体からはじまる表現世界の「見えぬけれどもある」を、共創の新たな知と手法で描き出す。心あるさまざまな共創の現場を、もっともっと元気にしていきたいのです。どうかご一緒に!

副会長
三輪 洋靖 Hiroyasu Miwa
産業技術総合研究所 主任研究員
<専門分野>サービス工学、人間工学、ロボット工学
<プロフィール>2001年早稲田大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。2004年同後期課程単位満了退学。同年9月学位取得。博士(工学)。早稲田大学理工学部機械工学科助手、早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構客員研究助手を経て、2005年4月産業技術総合研究所に入所。2018年11月より同所人間拡張研究センターにて、介護サービスを中心にサービスプロセスの可視化、従業員支援に関する研究、嚥下機能の計測とモデル化に関する研究等に従事。
<メッセージ>介護サービスでは、介護士、看護師等の介護スタッフ間のみならず、高齢者や家族も含めた、相互コミュニケーションや気付き、信頼関係がとても重要であることを肌で感じています。共創学会では、こうした現場の人達が生き生きと活躍できる場作り、サービス作りのための議論をしたいと思っています。

理事
秋田 有希湖 Yukiko Akita
鶴見大学短期大学部 准教授
<専門分野>身体表現論、舞踊学
<プロフィール>お茶の水女子大学大学院博士前期課程修了。修士(人文科学)。2010年より鶴見大学短期大学部専任講師。2018年より准教授となり、現在に至る。子どもや親子、保育・教育現場の身体表現研究を進めながら、被災地や公立文化施設等でインクルーシブな表現活動のファシリテーションを磨く。2021年より障害者就労支援センターでの実践をスタート。NPO法人みんなのダンスフィールド副理事長。
<メッセージ>あらゆる差異を超えて様々な人と出会い、表現を通して、この世界の新しい見え方に触れることが好きです。身体は、表現の現場で生じる出来事を確かに知覚しますが、その実際は、自分自身でさえもよくわからないことが多くあります。みなさんと一緒に、共創表現のリアルに迫ることができればとても幸せです。どうぞ宜しくお願い致します。

理事
浅井 忍 Shinobu Asai
草苑保育専門学校 専任講師
<専門分野>幼児教育学、保育学
<プロフィール>東洋英和女学院大学大学院人間科学研究科人間科学専攻修士課程、修了。幼稚園教諭12年・保育士4年の経験後、2015年から草苑保育専門学校で保育者養成に携わり、同時期から日野台幼稚園で子どもたちとの関わりを継続している。
<メッセージ>フィールドは、保育士・幼稚園教諭を養成する専門学校と、入園前のプレ保育を行う幼稚園の2箇所です。子どもを取り巻く環境にいる学生・保護者・教職員とつながりながら、感覚と身体について模索しています。現場での実体験を大切に、様々な人とのつながりを、あたため、循環していきたいです。人と人のあいだで蠢めくものについて、皆さんと一緒にお話できたら嬉しいです。

理事
植野 貴志子 Kishiko Ueno
ノートルダム清心女子大学 教授
<専門分野>社会言語学、語用論
<プロフィール>日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻博士課程後期満期退学。博士(文学)。日本女子大学助教、東京都市大学教育講師、順天堂大学准教授を経て、2018年より現職。論文に「日本語と英語における自己の言語化―「場所」に基づく一考察」(『場と言語・コミュニケーション』ひつじ書房、2022年)、「会話におけるストーリーの共創」(『共創学』1(1)、2019年)など。
<メッセージ>ことばの現象を研究しています。ことばの成り立ちにも、何気ないことばのやりとりにも、身体性、他者性、無意識、自然などの暗在的なはたらきを含んだ「共創」が潜んでいるように思われます。共創の論理を探究しながら、互いに手を差し伸べあえる共存在のあり方を考えていきたいと思います。

理事
大塚 正之 Masayuki Otsuka
早稲田大学 招聘研究員 / 弁護士
<専門分野>家族法、臨床法学
<プロフィール>東京大学経済学部卒業後、裁判官、早稲田大学大学院法務研究科教授を経て現職。筑波大学法科大学院講師、場の言語・コミュニケーション研究会員。主著「判例先例渉外親族法」(尾中郁夫学術奨励賞)、「場所の哲学ー存在と場所」、「場所の哲学ー近代法思想の限界を超えて」など。
<メッセージ>本学会の「共創」は、「場」と共に、前近代社会と近代社会の対立・矛盾を止揚し、次世代の学問を基礎づける根底をなすタームです。 近代社会・近代科学を超えるためには、自然科学・社会科学・人文科学の枠組みの向こう側の世界=臨床の知を探求することが必要です。 本学会を通じて新しい世界像をともに創りましょう。

理事
加藤 健治 Kenji Kato
国立長寿医療研究センター ロボット臨床評価研究室長
<専門分野>生活支援ロボット、福祉工学、神経生理学
<プロフィール>2009年に慶應義塾大学理工学部を卒業後、2011年に同大学大学院理工学研究科修士課程を修了し、2014年に総合研究大学院大学で博士(理学)を取得。現在、国立長寿医療研究センターの健康長寿支援ロボットセンター室長を務める。近年は、JSTムーンショット型研究開発事業(目標3)の課題推進者として、高齢者の活力を高め、挑戦を後押しする次世代型ロボット技術の開発と評価に取り組んでいる。その一環として「リビングラボ」を設立し、産学官連携による次世代技術の社会実装を推進している。
<メッセージ>高齢者の挑戦を後押しするロボット技術の可能性を追求しています。日常生活の支援にとどまらず、一人ひとりが新たな可能性に挑戦できる社会を目指し、さまざまな方々と共創を進めていきます。心と体に寄り添う技術の革新を通じて、世代を超えた支え合いを実現する社会づくりに貢献し、共創の未来を切り拓いていきたいと思います。

理事
小井塚 ななえ Nanae Koizuka
東洋英和女学院大学 専任講師
<専門分野>音楽教育学
<プロフィール>東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程、博士課程を修了。博士(学術)。2017年より現職。演奏家が聴き手の元へ出向き音楽を共有する「アウトリーチ活動」を自身のライフワークとして研究活動、音楽活動を展開してきた。現在は、子どもたちとのやり取りの中で生まれた様々なアイディアを学生や現場の先生方と共有発展させていくこと、そして多様な子どもたちとの音楽の場の創出をテーマに音楽ワークショップを展開するなど奮闘中。
<メッセージ>2017年3月、共創学会設立記念大会に参加した際の高揚感を今でもよく覚えています。学問の垣根を越えて人の営みを捉えようとする研究者や実践者お一人お一人の生き生きした姿がその場を作っていたのだろうと思います。私自身は音楽すること、人、場に興味があり研究や実践活動を続けてきました。様々な人と出会い、対話を重ねながら表現することや共創について探求していきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
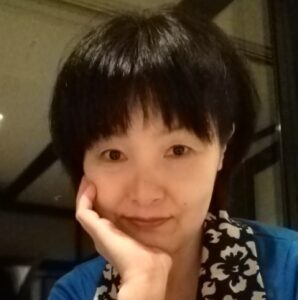
理事
佐々木 美加 Mika Sasaki
明治大学 専任教授
<専門分野>社会心理学、行動学
<プロフィール>九州大学文学部卒、大阪大学大学院人間科学研究科博士前期課程修了、東北大学大学院文学研究科単位修得退学、博士(文学)。近畿大学青踏女子短大(現文芸学部)、東北福祉大学総合福祉学部、常磐大学人間科学部を経て2008年明治大学商学部専任准教授、2013年~専任教授。2014年SFSU客員研究員。2019年~関西大学ソシオネットワーク戦略研究機構研究員。専門は社会心理学。認知‐行動プロセスを研究する。主著は『協調か対決か:コンピューターコミュニケーションの心理学』『交渉の心理学』『金融行動の心理学』。
<メッセージ>いつの時代でもどのような場でも共創があってこの世界は成り立っています。同じ事態に共に取り組んでも、その事態をどう認知するかで行動は変わります。更にその認知傾向には個人差があり行動パターンを形成しています。心理学では認知傾向や行動パターンの個人差を測定する心理尺度を開発できます。こうした心理尺度を調査実験から研究開発し、個々人の認知‐行動パターンを得点化・可視化して共創が進む社会に貢献して参ります。

理事
澤 宏司 Koji Sawa
数々企画 代表
<専門分野>数理科学、数理論理学
<プロフィール>1994年早稲田大学理工学部数学科卒。2010年神戸大学大学院理学研究科地球科学惑星科学博士後期課程修了。博士(理学)。首都圏の私立高校、大学を経て、2019年4月から現職。最近は論理と時間・空間の関係に関するモデルの研究に従事。簡単な計算を伴う全身運動プログラム「サワ☆博士の数楽たいそう」主宰。
<メッセージ>非論理的に論理について考えています。個人的な論理は有益なものにはなりがたく、より普遍的な論理の出現は他者の存在を前提とする点で共創的です。論理の生成に共創が関与しているだけでなく、十分に発達した共創の場の1つの表現が均一的な時間や空間なのかもしれません。

理事
戸田 祥子 Shoko Toda
宮城県立石巻支援学校 教諭 / 「てあわせのはら石巻・東松島」運営委員
<プロフィール>宮城教育大学教育学部養護学校教員養成課程卒業後、岩手県の小学校教諭を経て、支援学校などで学級担任として障害のある子どもたちの教育を行う。重度の自閉症を伴う知的障害のある子どもの母親でもある。東日本大震災後は石巻市・東松島市で障害のある子どもたちや家族と一緒に「てあわせ・のはら」の活動を継続し、県内外の福祉施設や団体と連携しながら活動の輪を広げている。
<メッセージ>問題や困ったことが起きたとき、「これからどうするか?」と考え、「いま何ができるのか」を選びながら手探りで進んできました。2011年の東日本大震災の際は東松島市の自宅が被災し、重度の自閉症を伴う知的障害のある息子は、避難所でパニックを起こしました。いろいろな出会いに支えられ現在に至っています。多様な人々が共に表現を創り合う活動から多くを学び、現在は「自分を表現する」ことが、私にとっても息子にとっても生きていくのに欠かせないことだと感じながら過ごしています。

理事
永田 鎮也 Shinya Nagata
一般社団法人共創基軸 代表理事・会長
<専門分野>薬理学、電気生理学、生体情報工学、薬剤師、博士(薬学)
<プロフィール>製薬企業で昇圧剤、降圧剤、救急車搭載医療機器、生体信号ゆらぎ解析ソフトを研究開発・製品化。研究開発・生産の統括責任者、総括製造販売責任者、 責任技術者を務め、2016年4月より現職。場の研究所理事、新共創産業技術支援機構副理事長、SSJP超音速機事業企画研究会メンバー、東本願寺別院僧侶・総代役員、 関西柳生会初代代表、科学技術振興機構プロジェクトメンバー(2001~2003年)。国連、ITU、国内外の学会、大学等で講演多数。
<メッセージ>国家戦略に共創が謳われ、概念の深い理解と発展が求められています。これら状況を背景に、共創の概念と言葉を創案された佐々木正先生が、 共創を超える実践的学会の立ち上げを強く希望されました。本学会は研究会に止まらず、実践知を耕す学会にしたいと思います。研究者に限らず、様々な分野の方々のご参加を切望します。

理事
福田 大年 Hirotoshi Fukuda
札幌市立大学 准教授
<専門分野>情報デザイン、デザイン教育、遊びのデザイン
<プロフィール>デジタルコンテンツ制作会社の共同設立後、専任講師を経て現職。博士(システム情報科学)。当事者がいる現場の資源を活用した表現活動を介した協働的営み(協創)の研究中。子どもと段ボールでつくる遊び場(キッズデザイン賞)、障がい者と考案した描画対話(協創スケッチ法)、アナログ資源とデジタル技術を連動させた遊び創作ができるアプリ開発(特許取得)、札幌市円山動物園ホッキョクグマ館サイン計画監修などを手掛ける。
<メッセージ>身の回りのヒト・モノ・コトは、相互に交わりながら単独では生み出せない豊かな営みを創り出していると思います。道端に咲く花を見つけて楽しむように、日常生活の何気ない営みにも目を向け、多様な人との対話から新しい可能性をひらいていくことも、共創の一つの在り方だといいなぁ〜という妄想を持ちながら試行錯誤しています。新しい共創の在り方を模索する対話の場を、本学会でよりたくさん生み出す一助になれたらと思います。

理事
三輪 敬之 Yoshiyuki Miwa
早稲田大学 名誉教授
<専門分野>共創学、生命機械工学
<プロフィール>早稲田大学名誉教授。1947年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科博士課程単位取得退学後、同大学助手・講師・助教授を経て、1986年に理工学部教授、学部再編で2007年より創造理工学部教授。工学博士。日本機械学会フェロー。日本ロボット学会、ヒューマンインタフェース学会などの理事を歴任。2017年4月「共創学会」初代会長に就任し、2025年3月まで4期にわたり務めた。1986年Moët-Hennessy 最優秀科学賞を受賞(植物生産分野)。シャドウ・メディアによる上演や体験展示を国内外で実施。共著書に『場と共創』(NTT出版)、『あっ!Becoming』(勁草書房)など。
<メッセージ>8年間,会長を務めさせていただきました。この間,会員の皆様のご期待に応えられたかどうかは心許ないのですが,多様な人々が集い議論する場は,他の学会にはあまり見られないものだと感じています。共創学はいまだ確立された学問とは言えませんが,むしろそれは,他者の異質性を介して立ち上がってくるものなのかもしれません。学会そのものが,これからも共創らしく在り続けることを,心より願っております。

理事
山口 友之 Tomoyuki Yamaguchi
筑波大学 准教授
<専門分野>ロボティクス,ヒューマンインタフェース,画像工学
<プロフィール>2002年早稲田大学理工学部機械工学科を卒業、2004年同理工学研究科修士課程修了、2007年同博士課程修了。2008年3月博士(工学)。早稲田大学理工学術院客員研究助手、同大学理工学術院助手、同大学次席研究員を経て、2013年筑波大学システム情報系助教。2011年から2013年米国カーネギーメロン大学客員研究員。メディアインタフェース(TwinkleBall、おいしさインタフェース)、実応用情報処理技術(劣化検査作業支援)、ロボティクスの応用研究等の研究に従事し、身体を含んだ人間の機能と感覚の工学的な知見に基づいた人間系と機械系の新しいコミュニケーションを築く研究に取り組む。
<メッセージ>コミュニケーションには、自分自身とのコミュニケーションと他者とのコミュニケーションがあります。内外のコミュニケーションから共創を考えるにあたり、自分の想像と出力された表現との違いによるギャップや、自分と他者との違いによるギャップなど、これらの違いを知覚することが共創への一歩だと思います。共創するインタフェースを追求する上で、これらの違いを許容するのか埋めるのか等、学際的な視点から思考したいと考えております。

理事
横溝 賢 Ken Yokomizo
札幌市立大学 准教授
<専門分野>情報デザイン、社会実践のデザイン学
<プロフィール>グラフィックデザイナとして広告代理店に務めた後、渡伊。現地にて多様な専門家との協働デザインプロジェクトに複数携わり、社会実践のデザイン思想と技術を学ぶ。帰国後、八戸にて、一次産業の現場で地域志向のデザインマインドを涵養するデザイン教育を展開。一連の実践アプローチを研究し、博士(工学)を取得。現在は札幌市立大学に拠点を移し、地域の人びと共にその土地の生活世界を描きなおす社会的なデザイン研究をおこなっている。
<メッセージ>ある土地をあるく-それは私と場所が結びつく行為であると考えています。おなじ土地を歩いた人と, 自らの経験を語りあってみると、私-たちの場所〈現場〉がそこに現れます。「あれ=共創する時空」はそこに現れたような気がするのです。共創学会には、いろいろな〈私ーたち〉の場所がもちよられます。ここでの学会活動を通じて、「あれ」がなんななのか、その成り立ちを解明したいと考えています。

監事
岡本 誠 Makoto Okamoto
公立はこだて未来大学 特命教授
<専門分野>情報デザイン、知覚デザイン
<プロフィール>1986年筑波大学芸術研究科修士課程修了。1986年から富士通株式会社総合デザイン研究所。2000年から公立はこだて未来大学教授。2022年から公立はこだて未来大学特命教授。暗闇の環境を非接触で触る装置、気配を感じる装置など研究中です。函館市のまちぐらし活動、市民共創ものづくり活動(函館工作座)、障害者社会連携などの共創活動を実践中。
<メッセージ>皆で何かを作ると、お互いを理解することができて、同時に新たな気づきを得ることができます。手間はかかりますが良いデザイン成果に辿り着けると思います。手間や困難を乗り越えるのは大変ですが、困難の過程で人の内面や関係が少しずつ変化していくのは興味深いです。学会での多様な議論を楽しみにしています。

監事
金尾 雄二 Yuji Kanao
障害者総合支援法指定事業所「からしだね」所長
<専門分野>障がい者福祉、高齢者福祉
<プロフィール>1973年早稲田大学大学院修士課程機械工学専攻修了後、(株)日立製作所入社。亀有工場、土浦工場にて高速増殖型原子炉用ナトリウムポンプの研究・開発・設計および沸騰水型原子炉用各種ポンプの保守・補修・設計に従事。 1984年に退職し日本同盟基督教団土浦めぐみ教会事務長に就任、1987年に教会付属マナ愛児園設立、2003年に介護保険法指定事業所「喜楽希楽サービス」設立・所長。2010年に退職し東京基督教大学神学部国際キリスト教福祉学科入学。 2013年卒業後は、社会福祉法人等にて障がい者福祉に従事後、2015年に土浦めぐみ教会に障害者総合支援法指定事業所「からしだね」を設立、2017年6月には児童福祉法指定事業所「からしだね」を設立して現在に至っている。
<メッセージ>異質な顔写真で申し訳ありません。東日本大震災の折に10m近い津波に覆われた突堤の上に立って、放射性物質拡散事故を起こした福島第一原子力発電所を背景にして撮った自撮り写真です。 妻の実家は原発から約3㎞のところにありましたが、今は町全体が帰還困難区域に指定され家族をはじめ町民全員が故郷を失ってしまいました。一方私は、福島第一原発4号機を設計・製作した会社の一員として原発に関わる仕事をしていました。 このことから、「科学・技術と人間生活の間のコミュニケーションのあり方」を考えるようになりました。「共創」から生まれるものが「リアルな愛である」ことを期待しつつ、 障がいのある方々と互いに生きる喜びを毎日少しずつ味わわせていただいています。
| 相澤 洋二 | 塩瀬 隆之 | 野家 啓一 |
| 合庭 惇 | 塩谷 賢 | 橋本 周司 |
| 石井 淳蔵 | 菅野 重樹 | 藤井 洋子 |
| 稲葉 俊郎 | 菅原 和孝 | 本間 大 |
| 井野 秀一 | 諏訪 正樹 | 前川 正雄 |
| 大澤 真幸 | 高西 淳夫 | 茂木 健一郎 |
| 大塚 博正 | 津田 一郎 | 持丸 正明 |
| 岡田 美智男 | 永沼 充 | 米岡 利彦 |
| 片桐 恭弘 | 中村 美亜 | 渡辺 和子 |
| 金尾 雄二 | 那須原 和良 | 渡辺 富夫 |
| 喜多 壮太郎 | 西井 涼子 | |
| 桑原 知子 | 西平 直 |